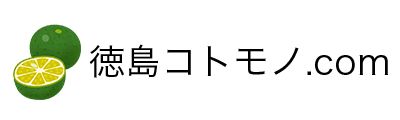今回は、鳴門市ドイツ館について記事をまとめていきます!
さて、徳島とドイツってどんな関係があるのでしょう。
鳴門市とドイツ館って関係があったんだ、など疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
鳴門市にドイツ館が建っているということは、何かしらの関係があったことは間違いなさそうですよね。
その関係とは何なのか。
ということで今回、鳴門市ドイツ館について調べてみました。
では早速見ていきましょう♪
所在地
鳴門市大麻町桧字東山田55-2
アクセス

車
- 高松自動車道「板野」IC より約10 分
- 徳島自動車道「藍住」IC より約15 分
- 神戸淡路鳴門自動車道「鳴門北」ICより約40分
- 鳴門市内中心部(市役所周辺)より約20分
JR 高徳線「板東」駅
- 駅より徒歩にて約25 分
- 板東駅よりタクシーにて約5分
路線バス
- JR 鳴門駅より徳島バス鳴門大麻線「ドイツ館」 下車
高速バス
- 鳴門西バス停より徒歩約15 分
空路
徳島阿波おどり空港よりタクシーにて約30 分
利用案内
観覧料
■鳴門市ドイツ館
大人:400円
小中学生:100円
団体(20名以上):大人320円、小中学生80円
■鳴門市ドイツ館と鳴門市賀川豊彦記念館共通券
大人:500円
小中学生:150円
団体(20名以上):大人400円、小中学生120円
■鳴門市ドイツ館と渦の道共通券
大人:730円
開館時間
9:30~17:00(入館は16:30まで)
休館日
第4月曜日(祝日の場合はその翌日)年末12月28日~12月31日
※その他、天災などの都合により、予定なく休館となる場合があります。
歴史(概要)

鳴門市ドイツ館は、板東俘虜収容所で過ごしたドイツ兵たちの活動の様子や、地域の人々との交流の様子を展示した史料館のこと。
かつて鳴門市大麻町(当時の板野郡板東町)には、大正6年~大正9年(1917年~1920年)のおよそ3年間、第一次世界大戦時に日本軍の捕虜となったドイツ兵を収容した「板東俘虜収容所」が存在。
板東俘虜収容所では、盛んだった音楽活動において、ベートーヴェンの「交響曲第九番」を、アジアで初めてコンサートとして全楽章演奏されたことでも有名。
こういった歴史と音楽の結び付きもあって今の時代に繋がり、とくしま88景にも選定されています。
日本初の第九演奏

ここ鳴門の板東俘虜収容所で、1918年6月1日に日本で初めてベートーベン作曲「交響曲第九番」が演奏されたことにより、鳴門市が日本初演奏の地となっています。
この事実は1941年に、この初演の2ヶ月後に板東収容所で「第九」(第1楽章のみ)を聴いた徳川頼貞が書いた『薈庭楽話』で明らかにされていましたが、長く無視され、1990年代になってようやく脚光を浴びることになりました。
なお、鳴門市では、国内で初めて演奏された6月1日を「第九の日」と定め、6月の第一日曜日に、県内外から500余名の合唱団が合流して演奏回を開催している。
今でもこうやってその日を大切にしていることが素敵ですよね♪
姉妹都市
1974年に鳴門市とドイツ・リューネブルク市との間で姉妹都市盟約が締結。
鳴門市では、ドイツ村公園の建設を始め、ドイツと共同でドイツ兵士合同慰霊碑(1976年)や、ばんどうの鐘(1983年)などを建立し、1993(平成5)年には鳴門市に新しいドイツ館が完成し、文化、芸術、教育、スポーツなどの交流が続けられている。
施設紹介
■1F
インフォメーション
小会議室
大会議室(大ホール)
ニーダーザクセン州展示コーナー
ミュージアムショップ

■2F
史料展示室
第九シアター
企画展示室

周辺スポット
鳴門市賀川豊彦記念館
道の駅第九の里(ベートーヴェン像、ばんどうの鐘)
ドイツ村公園(ドイツ兵慰霊碑、赤十字ゆかりの地モニュメント)
ドイツ橋、めがね橋
ひとり言
鳴門市とドイツの関係は、第一次世界大戦時に日本軍の捕虜となったドイツ兵を収容した「板東俘虜収容所」から始まっていたんですね。
その時代に生きてもなく、体験もしていない私がひとり言を言うのも恐縮するのですが、その時代があったことにより今日の鳴門市とドイツ・リューネブルク市が姉妹都市の関係にあるわけですよね。
そして、日本初の第九演奏という歴史も残ったんですね。
その次代に起こった事柄や文化にはいつも何らかの理由があって、その物事の裏側や経緯について注視すれば、もう少し世界の見え方が変わってくるのかもしれませんね。
歴史から学ぶことはやはり沢山ありそうです。